画像引用元:五大浮世絵師展公式サイト
こんにちは、カギ尻尾です。
「五大浮世絵師展―歌麿、写楽、北斎、広重、国芳」は、2025年.5/27-7/6まで上野の森美術館で開催していた展覧会です。
今回は、実際に五大浮世絵師展へ行って感じることがたくさんあったのでレビューします。
また、当展覧会では会期中に公式図録が売り切れてしまったので、購入したくてもできなかったというかたもいらっしゃると思います。そこで今回は、公式図録が買えるサイトもご紹介します。(*購入予約ができるのは 7/11金曜日までです*)
「展覧会には行けなかったけど図録は見たい」というかたも、よかったらご確認ください!

まず公式図録を購入したいという方は、こちらが公式で案内しているサイトです!⇩⇩⇩
”「五大浮世絵師展」の公式図録は、会場での販売分が完売につき販売を終了いたしました。現在、神戸新聞社運営のオンラインショップ【いいモノがたり】にて、7月11日(金)までの期間限定の予約販売を実施しております。商品は8月中に発送予定です。図録予約販売はこちら”
「五大浮世絵師展」がすごかったこと3つ!
「五大浮世絵師展―歌麿、写楽、北斎、広重、国芳」は、2025年.5/27-7/6まで上野の森美術館で開催していました。
さっそく、この展覧会の何がそんなにすごかったのかをお伝えしたいと思います。
五大浮世絵師展は質とボリュームがすごい
今回の展覧会は、「江戸の浮世絵師といえば誰?」と質問したら必ず名前があがるであろう、めちゃくちゃ有名な5人の絵師の浮世絵が一堂に会していました。
しかも、約140点におよぶ代表作が展示されているという、質・ボリュームともに充実した展覧会でした。
会場で撮影が許可されていた作品をこちらに載せておきます。どれも、どこかで目にしたことがある有名な浮世絵だと思います。
こちらは、写楽の「三代目坂東彦三郎の鷺坂左内」

寛政6年(1794)
版元:蔦屋重三郎
こちらは、北斎の「冨嶽三十六景 五百らかん寺さざゐどう」

天保2年(1831)頃
版元:西村屋与八
こちらは”昭和24年に切手の図案になったことでも広く知られる”広重の「月に雁」

天保5-6年(1834-35)頃
版元:川口屋正蔵
こちらは、国芳の「小子部栖軽豊浦里捕雷」
この難しい題名は「ちいさこべの すがる とよらの さと に らいを とらう」と読むようです。
小子部とは、少年たちで構成された古代日本の職業のことで、栖軽はこの絵の人物の名前と思われます。豊浦里は地名で、捕雷は雷を捕えるという意味みたいです。

天保7-8年(1836-37)頃
版元:西村屋与八
五大浮世絵師展は鑑賞しやすい展示方法がすごい
この展覧会は、展示方法に工夫がされていて、とても観やすかったです。
絵師ごとに章立てで構成され、壁面が色分けされていました。
おかげで、すごい混雑の中でも迷うことなく鑑賞することができたことがすごいと思いました。
さらに、その壁面の色も、それぞれの絵師を思い浮かべることができるようなぴったりの色だったので、遠くからでも見つけやすかったです。あえて順路に沿って行かず、「比較的空いている上の階から行こう」など、効率よく鑑賞することができました。
さらにさらに、どの壁紙の色も作品を邪魔することなく、むしろ雰囲気を盛り上げ、かつ、日本的で美しい色彩が採用されていたところにも感動!!

この展覧会を準備された方々の気持ちが伝わってくるようでした。
次項ではそれぞれの絵師ごとに、絵師の特徴や、当展覧会での壁紙の色・キャッチコピー・ハイライトをまとめましたのでご覧ください。
五大浮世絵師展は江戸の多様な視覚文化に迫る内容ですごい
「五大浮世絵師展」は、江戸後期の多様な視覚文化に迫る贅沢な内容でした。
風景画では「あ〜この場所ってあの辺だよね」とか「お〜江戸の時代はここもこんなに自然だらけだったんだ」と、単純ですが知っている場所の絵を見つけると感慨深いものがあります。
人物画ではなんと言っても着物の柄とか着こなしが素晴らしかったです。
巷でよく聞く「江戸の人たちは粋でおしゃれとはこのことか」と思いました。
また、人物と一緒に描かれている小物もいいんですよね。うちわとか縁側とかそういう物のひとつひとつがたまりません。
私ごとですが骨董が好きなので、そのへんも大変に楽しめた点でした。
「五大浮世絵師展」での壁紙の色・キャッチコピー・ハイライトと絵師の特徴
ここからは、それぞれ絵師ごとの「特徴」や、当展覧会での「壁紙の色」・「キャッチコピー」・「ハイライト」をまとめましたのでご覧ください。
| 絵師 | 壁の色 | 展覧会のキャッチコピー 絵師の特徴とハイライト |
| 「喜多川歌麿」 | ベージュ | ”物想う女性たち” 繊細な筆致と内面を映し出すような表情描写で知られる歌麿 「ばくれん」と呼ばれる酒好きの粋な女性が酒を豪快にあおるなど、女性の生き生きとした一瞬をとらえた印象的な作品群 |
| 「東洲斎写楽」 | ピンク | ”役者絵の衝撃” 活動期間はわずか10か月ながら145点の大首絵を遺し、忽然と姿を消した謎多き巨匠・写楽 俳優の“顔”を誇張し、迫力ある劇の臨場感を強烈に伝える作品群が展示 |
| 「葛飾北斎」 | ブルー | ”怒涛のブルー” 長寿だった北斎ならではの70代以降の斬新な色彩表現 藍色の濃淡を生かした空や波、誰もが知る『冨嶽三十六景』などの風景画がずらり 当時の絵手本として弟子たちに影響を与えた『北斎漫画』も展示 |
| 「歌川広重」 | グリーン | ”雨・月・雪の江戸” 各地を独自の筆致で表現し「浮世絵風景画」を確立した広重 旅ブームに乗って描いた『東海道五拾三次』や『名所江戸百景』から、静と動を対比させた名品が展示 |
| 「歌川国芳」 | レッド | ”ヒーローとスペクタクル” 斬新な構図の武者絵や、独特な風刺画で浮世絵の新境地を開いた国芳 武者絵、戯画、動物画、妖怪画などジャンルを超えた展示 骸骨をはじめ独創的なモチーフも多く、江戸のユーモアが感じられる |
「五大浮世絵師展の図録が買えるサイトはここ!」
今回の展覧会で個人的に残念だった点はこれ、「図録が売り切れていて買えなかった!!」こと。
会期の終盤に(7/4金曜)行ったのも悪かったのですが、まだ土日も残ってるのに・・・、ないの?
美術館内のショップも大混雑だったので、今回の展覧会の人気の高さがうかがえます。
私と同じように「図録買うべし」と勇んでショップに行ったのに売り切れの報を聞き、がっくり肩をおとした同志がたくさんいることでしょう。
大丈夫です!今月 7/11金曜日までなら同じ図録を買えるネット通販がありますよ。
ちなみにこのサイトは美術館でアナウンスしている公式なので、安心面でもお墨付きです。
ただ、気になる点がふたつほど。
ひとつは、送料が500円かかること。
’’送料は全国一律で1冊500円となります(2冊以上は注文時にご確認ください)。’’
とのことです。
(まぁね、送ってもらえるなら楽ですな、図録って重いし・・・と、納得することもできる。)
もうひとつは納期が遅いこと。
”お届けは8月中を予定しております”
とのことです。
(え〜8月中って上旬と下旬ではずいぶん違うけども・・・、でも確実に新品を手に入れることができると、納得することもできる。)
実は、もっと早く手にいれることはできまいかと、ヤフオクやメルカリなどを探してみましたが、早く手には入るものの値段がめちゃくちゃ高くて断念しました。私が見たものは10,000円以上していました・・・。
もちろんAmazonと楽天市場はいの一番に確認しましたが、取り扱いはなく、今のところ中古でも見つかりませんでした。(7/9現在)
オークションサイトなどで定価で即日出荷してくれる出品者さんが見つかればかなりラッキー。
もしそうでなければ公式での購入を検討してみてくださいね。
公式:神戸新聞社運営のオンラインショップ【いいモノがたり】
*購入予約ができるのは 7/11金曜日までです*
まとめ
「五大浮世絵師展」は、美人画、役者絵、風景画、武者絵など、各ジャンルの頂点に立つ絵師の代表作が一堂に会した魅力的な展覧会でした。
多面的に江戸時代の文化を知れる内容だったので、絵画ファンのみならず時代劇や骨董好きなど、様々な人が楽しめる内容だったと思います。
また、絵師それぞれの個性の対比もおもしろかったです。
5人の巨匠を章ごとに比較できる構成で、作風や発想の違いが際立っていました。
そして最終的な結論としては「歌麿、写楽、北斎、広重、国芳って、やっぱりすっっげぇ人たちだったんだな」ということ(チープな表現をお許しください)。
とにかく、筆遣いや構図、色彩、空気感の表現など、それぞれが持つ技術の高度さを実感した展覧会でした。

次回は、
「浮世絵のことをもっと知るために本を読んでみよう、でもどの本がいいかなぁ?」と迷っているあなたにおすすめの本をご紹介します📙
読んでくださった方の参考になるようにがんばるぞ、ぬん!
次の記事はこちら→『浮世絵のことをもっと知りたい!あなたにおすすめの本4選』
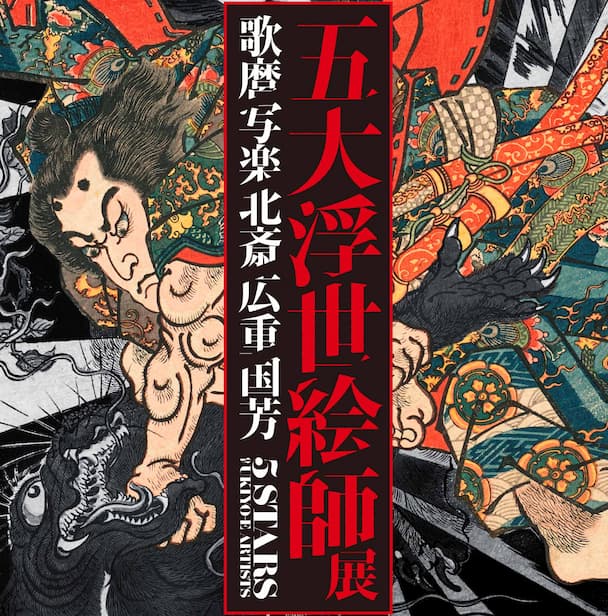

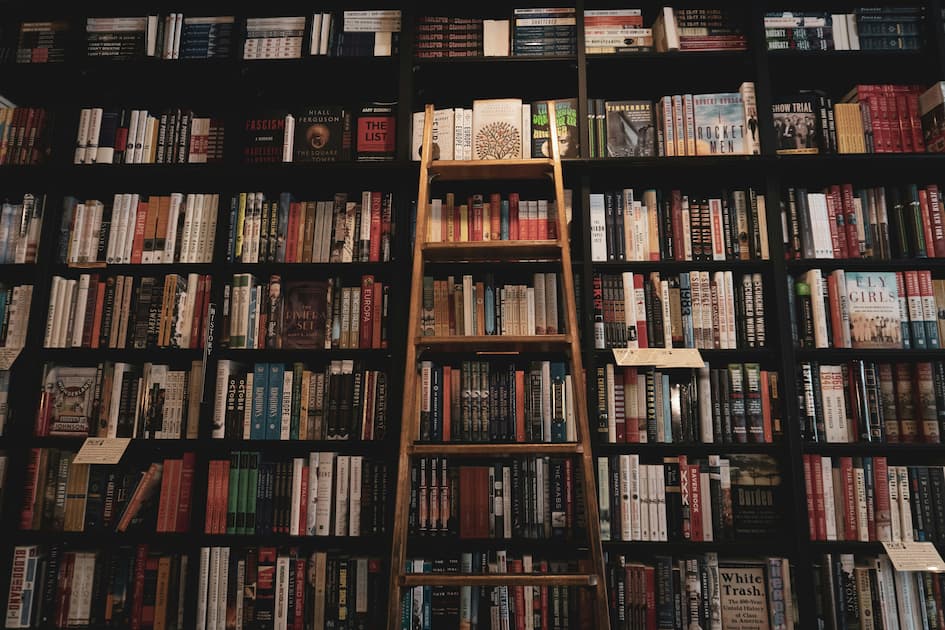
コメント