画像:「五大浮世絵師展」にて撮影 葛飾北斎「冨嶽三十六景 五百らかん寺さざゐどう」
こんにちは、カギ尻尾です。
「五大浮世絵師展―歌麿、写楽、北斎、広重、国芳」に行って以来、浮世絵の世界にすっかり魅了され、前回、前々回と浮世絵に関する記事を書いてきました。
今回は当サイトの本分である「額装」についてです。

15年間、作品を額縁にいれる「額装」の仕事をしていた私カギ尻尾
今回は、額装分野において特殊と言われている「浮世絵の額装」をテーマにお届けします
以前働いていた額縁店で、「浮世絵は飾って楽しむものじゃない、収集して楽しむもんだ」と教えてくれたお客さんがいました。
それは、浮世絵がとても繊細で、環境の影響を受けやすく、劣化しやすいものだからという理由で、インテリアとして飾るには向かないということでした。
ここ最近、浮世絵にハマり、片っ端から本を手に取り勉強していくうちに、本物の浮世絵は、他のアート作品と比べても特にデリケートなものだと理解するようになりました。確かに浮世絵は、長期間飾るには向いていないと思います。
でもここで疑問が浮かびます。
「何でもかんでも揃っている現代で、まだ、本当に、浮世絵って飾っちゃだめなの?」
そして出た結論は、
「それなりの装備と配慮があれば、浮世絵をインテリアとして飾って楽しむことは可能」だということです。
さっそく浮世絵の額装についてまとめることにしました。
5回のシリーズに分けた1回目である今回は、「浮世絵を対策なしに飾るとどうなるか」についてです。
大切な浮世絵を飾って楽しむためにはまず、「浮世絵の性質や、具体的にはどんなダメージが起こり得るのか」ということを知っておかなければなりません。
「そもそも、江戸時代 浮世絵とはどんなものだったのか?何からできていて、どう作られるのか?」という基本的なところから、じっくりと浮世絵を紐解いていきたいと思います!
今回の記事が、私と同じように「浮世絵をインテリとして飾りたい」と考えているあなたの参考になりますように。
そもそも浮世絵とはどんなもの?
まず、浮世絵について基本的なところを知っておきたいと思います。
「そもそも浮世絵が何からできていて、江戸時代どんな位置付けのものだったのか」というところから浮世絵を紐解いていきます。
江戸時代「浮世絵」はどんな位置付けだった?
浮世絵は江戸時代の人々の「今を楽しむ」文化を描いた絵で、いわゆる”大衆向けアート”でした。
江戸時代の浮世絵(特に「錦絵」と呼ばれる多色刷りの作品)は、庶民でも買える価格で販売されていました。
【浮世絵の価格の目安(江戸時代後期)】
1枚あたり約16文〜24文。
現代の価値にざっくり換算すると、数百円〜千円程度くらい。
例えば”そば1杯=16文”くらいだったので、「そば1杯分のお金で浮世絵が1枚買えた」感覚です。

ちなみに例外もあり、
・特別な装丁のもの(絵本や画帖)
・雑誌やカタログとして作られた豪華本(多色刷り・高級紙)
・有名絵師による限定数の作品
などは高額だったよ
【庶民向けの娯楽だった理由】
浮世絵は量産できる木版印刷だったため、コストを抑えて販売することができました。
歌舞伎役者や美人画は当時の「推し活」感覚。
風景画などは、「観光ポスター」の役割も担い。
壁に貼ったり、スクラップブックのように集めたりして楽しみました。
浮世絵は何からどうやって作られるの?
浮世絵は、「木版画」によって作られています。
使用される主な材料と工程をざっくりまとめると次のような感じです。
【使用される主な材料】
「版木」:山桜(硬くて彫りやすい)
「紙」:和紙(奉書紙など。丈夫で絵具との相性が良い)
「絵具」:天然顔料(鉱物・植物由来のもの、のちに輸入品も)
【浮世絵ができるまでの工程】
1.「絵師(えし)」: 下絵(墨一色)を描く。
浮世絵の原画作者、葛飾北斎・歌川広重・喜多川歌麿など、絵師の仕事です。
⇩
2.「彫師(ほりし)」:絵師の下絵をもとに、木の版木(通常は桜の木)に絵を彫る。
色ごとに別の版木を作成します。これは彫師と呼ばれる職人の仕事です。
⇩
3.「摺師(すりし)」: 彫られた版木に色を塗り、和紙に摺って完成させます。
手作業で何枚も摺り、仕上げます。これは摺師と呼ばれる職人の仕事です。
浮世絵の歴史
浮世絵は、17世紀後半(江戸時代初期)から作られ始めました。
おおよその始まりは 寛文年間(1661〜1673年)頃とされています。
浮世絵は「浮世草子」という小説などの挿絵から派生したアート作品です。
この「浮世」は当時、”「はかない世」から転じて、「今を楽しむ現世」”という意味になります。
最初の浮世絵は、手描きや、墨一色の(単色刷り)版画が中心でした。
18世紀初頭(1700年〜)本格的な木版画として発展し、役者絵・美人画が人気を博します。
1765年頃には「錦絵(多色刷り)」が登場し、現代でよく知られるようなカラフルな浮世絵に進化しました。
19世紀前半(1800年頃)に黄金期を迎え、風景画や歴史画など多彩に展開していきます。
そして、この頃には現代でも名を知られる有名絵師たちが揃います。

1781-1818年頃活動の「喜多川歌麿」:繊細な筆致と内面を映し出すような表情描写で女性を描く
1779-1849年活動の「葛飾北斎」:藍色の濃淡を生かした空や波、誰もが知る『冨嶽三十六景』などで知られる
1830-1844年人気の「歌川広重」:日本各地を独自の筆致で表現し”浮世絵風景画”を確立
1827-1850年活躍の「歌川国芳」:斬新な構図の武者絵や、独特な風刺画で浮世絵の新境地を開く
こんな錚々たる面々が揃ったよ!
浮世絵には何が描かれていたの?
浮世絵は、当時の人々の好みや流行を映したものが多く、「江戸のカルチャー雑誌」的な存在でした。
主なテーマには、
「美人画」:遊女や町娘など、江戸の美女たちの姿
「役者絵」:歌舞伎役者の人気シーン・ポートレート
「風景画」:富士山、名所などの観光ガイド的な絵(例:葛飾北斎『富嶽三十六景』)
「相撲絵」:人気力士の取り組みや肖像
「妖怪・伝説・歴史絵巻」:民間伝承や物語の挿絵
などがあります。
「浮世絵は飾るな」と言われる理由
ここからは、浮世絵の性質からくる「浮世絵はインテリとして飾るには向かない」と言われる理由や、「対策なしに飾るとどんなダメージが起こり得るのか」をお伝えしたいと思います。

風水や縁起の観点から浮世絵を飾る向き不向きについては別の専門サイトにお任せするとして、
ここでは「浮世絵の性質・特徴から発生する飾るリスク」に全振りしてお届けします
『浮世絵は紫外線に弱い』
まず、浮世絵は紫外線に非常に弱いという性質があります。
そのため”本物の浮世絵は、保存のため、額装・展示の期間を限定すべき”というのが一般的に言われていることです。
そもそも浮世絵は、保存を想定された芸術品ではなく、庶民向けの消費品として作られていた歴史があります。
素材も「長期保存に最適」というより、「刷りやすく、鮮やかで安価」という目的で選ばれているため、光に対して非常に繊細です。
紫外線が浮世絵に与えるとされる3つの具体的なダメージ例。
⇩⇩⇩
1.「顔料・染料の色あせ(退色)」
これが浮世絵を飾る上で、いちばんの問題と言っても過言ではありません。
浮世絵に使われている色の多くは、植物や鉱物由来の天然顔料や染料です。
特に江戸時代初期〜中期の浮世絵では、植物系の有機顔料(紅花、藍など)が多く使われており、これらは紫外線に非常に敏感です。
紫外線を浴び続けると、化学構造が壊れて色が分解されてしまうため、鮮やかな色が徐々にあせていきます。
例としては、
”赤系(紅花や朱など)は特に退色しやすい”
”青系(藍や群青)は比較的安定しているが、時間と共に変化することもある”
とされています。
2.「和紙自体の劣化」
和紙に含まれるセルロース繊維も、紫外線によって酸化・分解が進みます。
その結果、紙が黄ばむ・茶色く変色する(ヤケ)・もろくなる(脆化)といった現象が起こります。
3.「印刷材料・接着剤の劣化」
浮世絵の製作過程で使われたでんぷん糊や膠(にかわ)などの天然接着剤も、紫外線で化学分解されやすいです。
そのため、剥がれやにじみ、シミの発生につながることがあります。

📙浮世絵が紫外線に弱い理由【まとめ】📙
*天然顔料・染料が紫外線で分解されやすい
*和紙が紫外線で劣化・黄変・脆化する
*接着剤や印刷材料も紫外線に弱い
以上3つの要素が重なっているからなんだね
『浮世絵は湿気に弱い』
浮世絵の素材である「和紙」と「天然顔料・染料」などは、湿度の変化や高湿度環境に非常に敏感です。
湿気が浮世絵に与えるとされる4つの具体的なダメージ例。
⇩⇩⇩
1.「和紙の変質」
和紙は植物繊維(主に楮・三椏・雁皮)からできている天然素材のため吸湿性が高く、空気中の湿気を吸いやすいです。
湿度が高くなると、紙が膨張して、波打つ・反る・歪むといった変形が起こりやすくなります。
それなら乾燥させたらいいかというと、そうでもないのが難しいところ。
乾燥すると今度は縮むため、繰り返しの膨張・収縮で、紙がダメージを受けて脆くなることもあります。
2.「顔料・染料のにじみ・劣化」
浮世絵の彩色に使われている顔料・染料の中には水に溶けやすいものがあります。
湿気を吸って結露したり、水分が紙に入り込んだりすると、色がにじんでぼやけたり、絵が崩れたりする可能性があります。
特に植物性の染料(紅花など)は、水分で退色しやすいです。
3.「カビの発生リスクが高まる」
湿度が65%以上になると、和紙にカビが発生しやすくなります。
特に浮世絵に使われているでんぷん糊(米糊)や膠(にかわ)は有機物で、カビの栄養源になります。
カビは一度生えると色素や繊維を破壊し、絵が黒ずむ・染みができる・悪臭がするなど、深刻な問題です。
4.「虫(紙魚やチャタテムシなど)による食害が発生する」
湿度が高いと、カビを食べる虫(特に紙魚=しみ科の昆虫)が繁殖しやすくなります。
これらの虫は和紙や糊を食べてしまい、絵が破れる・穴が開く・輪郭が崩れるといった損傷につながります。

📙湿気による浮世絵のダメージ【まとめ】📙
*湿気を吸うと和紙が変形・波打つなど、和紙の変質が起こる
*水分により顔料・染料が変質し、にじみや色あせが起こる
*紙や糊がカビの温床になりやすい
*湿気が虫を呼び、紙を食べられる原因に
まとめ
今回は、
「そもそも、江戸時代 浮世絵とはどんなものだったのか?何からできていて、どう作られるのか?」というところから始まり、
浮世絵の性質からくる『浮世絵は飾るな』と言われる理由、「対策なしに浮世絵を飾るとどんなダメージが起こり得るか」など、
基本的なところから浮世絵を紐解いていきました。
終盤は浮世絵に関するネガティブ情報が多くなってしまいました。
こうなってくると「浮世絵ってやっぱり飾らない方がいいじゃん」「大事にしまっておけよ」ってなりそう。
たしかに、知れば知るほど浮世絵って本当に繊細で、飾るなと言われる理由も納得できます。
でも、だからこそ、飾る飾らない以前に、「どんなダメージが起こり得るのか」ということは知っておかなければならないと思います。
知識がなければ知らないうちに大切な浮世絵を痛めてしまう可能性もあるし、対策のしようもないからです。
浮世絵はあれこれ面倒くさいことがあるけど、浮世絵にしかない魅力があって、かつてモネやゴッホがそうだったように、浮世絵ならではの美に魅了されてしまいます。
浮世絵をインテリアとして飾って、生活に取り入れることができたら素敵だろうな、と思います。
次回は、いよいよ、現代の額装アイテムを駆使し環境を整えて、我らの浮世絵を様々な敵から守り、飾るための方法をご紹介します!

大丈夫!次回は浮世絵を飾るための具体的な対策をお話しします
読んでくださった方の参考になるようにがんばるぞ、ぬん!

浮世絵についてもっと知りたくなったあなたは、おすすめの本をまとめた記事をチェックしてみてくださいね!⇩⇩⇩

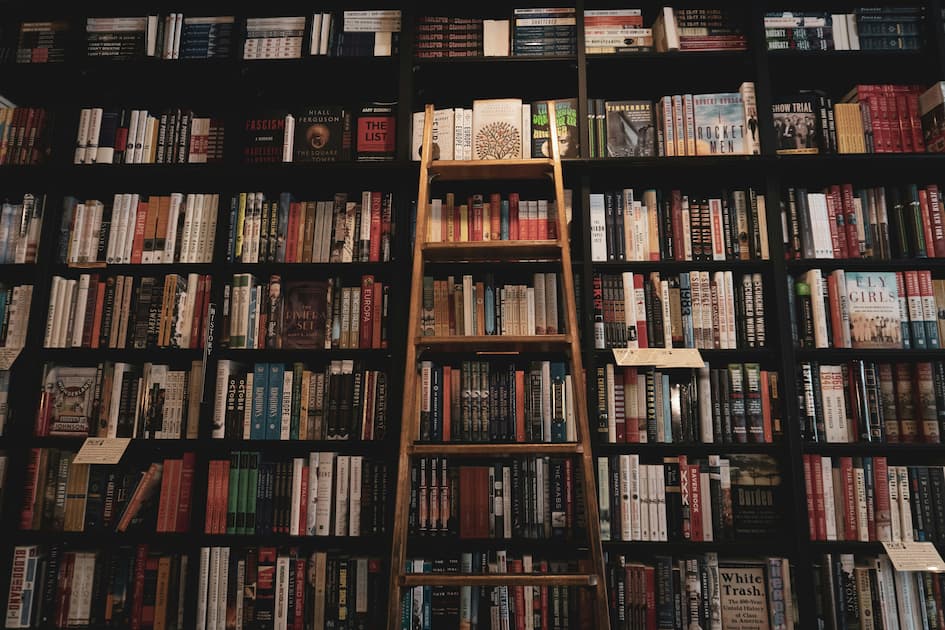

コメント